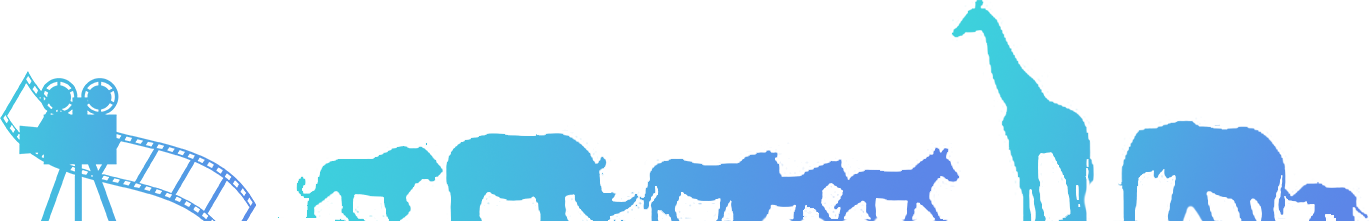美保 大学3年生

# 美保 大学3年生
# 第一章 友人との会話
大学のカフェテラスは、春の光で満ちていた。
植え込みの若葉が風に揺れ、ガラス越しに差し込む陽射しがテーブルの上で反射している。
陶器のカップが軽やかに触れ合い、学生たちの笑い声が風に運ばれて散っていった。
**美保は、丸顔の美人として知られていた。**
黒髪を耳にかけて笑うたび、上下左右の銀歯が自然光を受けてきらりと光を放つ。
上の奥歯にはクラウン、下の奥歯には大きなインレー。口を開くだけで、自然光を受けた銀が瞬き、彼女の柔らかな美貌に独特の影を添えていた。
「私ね、虫歯多いんだよね〜」
コーヒーをかき混ぜながら美保が言った瞬間、友人たちの視線が集まる。
「えっ、ほんと? そんなふうに見えないけど」
彩香が驚いたようにストローを指で回し、覗き込む。
「ちょっと、アーンして見せてよ」
美咲が茶化すように言い、奈緒も「見たい見たい!」と笑った。
美保は小さくため息をついてから、仕方なく口を大きく開けた。
「……アーン」
春の陽射しが真っ直ぐ差し込み、口の奥に銀が一斉に光を返す。
クラウンの表面は鏡のように周囲を映し込み、下のインレーは小さな星座のように並んで輝いていた。
「わぁ、すごい……ほんとにキラッキラ」
奈緒が顔を寄せて覗き込む。
「上も下もだね、奥までしっかり」
彩香は感心したように頷きながら、自分もいたずらっぽく口を開けた。
「私もね、ここに銀歯あるの。アーン」
奥歯に小さな銀の詰め物が光り、太陽の光で一瞬だけ星のようにきらめいた。
「ほんとだぁ」
美保は笑顔を作って同調した。けれど心の奥では血の気が引いていく。
――自分の口の奥でも、同じように銀が光っている。
――これからまた増えるのかもしれない。
「でもさ、歯医者ってほんと痛いよね」
美咲が声を落とした。「先週削られたんだけど、あの音……耳にキュイーンって響くの。涙が出そうになったんだから」
「やめて〜! 想像しただけで無理」
奈緒が両手で耳を塞ぎ、肩をすくめる。
「先生、『痛かったら手挙げてね〜』って言うけどさ、挙げても止まらないときあるんだよ」
彩香が苦笑する。
「“もう少しですからね〜”って、ずっと続くの」
「あるある!」
美咲がうなずく。
「待合室で小さい子が“いやだ!”って泣いた瞬間、奥からキュイーンって聞こえたことある。返事みたいで、私まで震えたよ」
三人の会話に、美保は笑顔を作って合わせた。
「……ほんとだよね」
だが心臓は早鐘を打ち、背中にじわりと汗が滲む。
カップの水を一口飲んだ瞬間、右下の奥歯がビリッとしみ、思わず肩が震えた。
――やっぱり……来てる。
――あの奥歯、もうダメかもしれない。
春の光は暖かいのに、銀歯の輝きと友人たちの体験談は、美保の胸を冷たく締めつけていった。
# 第二章 夜の不安(80点仕上げ)
夜の静けさは、ひときわ深かった。
窓の外で虫が細く鳴き、遠くの道路では原付が短く響いて、すぐ闇に吸い込まれていった。
机の上に広げたノートの文字は、ただ黒い模様にすぎず、どれも意味を結ばない。
耳の奥には――昼間の会話が残した音が潜んでいる。
――キュイーン。
ただの記憶であるはずなのに、鼓膜を震わせ、胸の奥に冷たい波を広げていく。
「……確かめないと」
声に出すと、吐息はかすかに震えた。
洗面所のスイッチを押すと、白い光がぱっと広がる。
タイルの壁は冷たく反射し、歯磨き粉の甘い香りと、金属の匂いが夜の静気に混じった。
鏡の前で唇を押し下げる。
「……アーン」
口を開いた奥に、影がひとつ沈んでいた。
右下の最奥――白い歯並びの端に黒い穴がぽっかりと口を開け、光を拒んでいた。
舌先で触れる。ざらりとした異質な感触に、肩がすっと強張る。
水を含めば、
「ビリッ」
氷の刃のような痛みが神経を走り、頭の奥へと突き抜けた。
「っ……」
鏡に手をつき、映る顔を見つめる。
目尻には涙が滲み、瞳は怯えを隠せなかった。
記憶が静かに開いていく。
――小学校の歯医者。
母に手を引かれ、消毒液の匂いにむせ返った。
診療台の革張りは冷たく、足は小刻みに震えてスニーカーの靴底が音を立てた。
「大丈夫だからね」と声をかけられた瞬間、耳を裂くように「キュイーン」が響き、泣き声が喉を破った。
押さえつけられた腕。胸の上の重み。
顎はこじ開けられ、白い無影灯が瞳に突き刺さる。
涙と金属の匂いが混じり合い、幼い体は逃げ場を失った。
――中学校の治療。
麻酔の針が歯ぐきに触れたときの冷たさを、いまも覚えている。
「痛くないですよ」と穏やかな声。
信じようとした。
けれどドリルが触れた途端、骨に響く痛みが全身を貫いた。
「ひっ……」息にならない声。必死に左手を挙げた。
だが音は止まらず、「もう少しですからね〜」と声だけが降ってくる。
涙が頬を濡らし、汗が制服の襟を重たくした。
閉じた瞼の裏で、光と音と痛みが渦を巻いた。
……二つの記憶が、鏡の中に重なった。
映るのは大学生の自分。
だが、その瞳の奥には泣き叫ぶ子供と、汗に濡れた制服の中学生が息づいていた。
「……いやだ」
小さな声が胸をふるわせる。
鏡の奥の黒い穴は、未来の姿を映す鏡のようだった。
そこに銀色が埋め込まれ、笑うたびにさらに光を増すだろう。
上下左右に銀歯が増え、口を開けば過去と痛みの記録が照らし出される。
――行かなきゃ。このままでは、もっと悪くなる。
――でも、あの音と痛みに、また耐えるのか。
指先は白くなるほど洗面台を握りしめ、肩は小刻みに震えていた。
蛍光灯の白は冷たく、涙で滲む瞳の中で、過去と未来が揺れ合っていた。
「……怖い」
その一言は夜の静けさに吸い込まれ、洗面所の冷気に溶けていった。
# 第三章 歯科医院の入口から待合室へ
午後の講義を終え、商店街を抜ける。
耳に入るはずの八百屋の呼び込みやパン屋の匂いは遠のき、心臓の鼓動だけが胸の奥で強く鳴っていた。
角を曲がったとき、白いタイル張りの建物が現れた。
「○○歯科クリニック」。
磨かれたガラス扉、青い文字の看板。奥には観葉植物と受付の影。
そのとき――
――キュイーン。
扉の隙間から漏れた音が、美保の耳に鋭く突き刺さった。
右下の奥歯がうずき、膝がわずかに震える。
「……大丈夫」
小さく声にしたが、声はかすれて空気に吸われた。
取っ手に手を伸ばすと、汗で滑り、指先がガラスを撫でただけで落ちてしまう。
スカートで手を拭き、もう一度握り直した。
深呼吸を三度。
息を吐くたびに胸の奥が冷えていく。
意を決して扉を押す。
冷房の風が頬を撫で、薬品と消毒液の匂いが鼻を刺した。
外界のざわめきは断ち切られ、ここは「治療のための世界」に変わる。
床のワックスは明るく光り、靴底が「きゅっ」と小さく鳴った。
受付で診察券を差し出すと、女性の指がカタカタとキーボードを叩き、番号札が渡された。
薄い紙なのに、掌の中では鉛のように重く沈んだ。
待合室に足を進める。
壁には花の写真、鉢植えの緑。
だがそこに漂うのは緊張の空気。
冷房の風は乾いていて、呼吸をするたびに喉がわずかに痛んだ。
ソファには三人の女性が座っていた。
母親の腕にしがみつく小学生の女の子。
大きな瞳には涙が溜まり、「いやだ……」と小声でつぶやきながら、母の服をぎゅっと掴んでいる。
――診療台の上で泣き叫んだ、小学生の自分と重なる。
制服姿の高校生。
頬を手で押さえ、もう片方の手は袖口をねじるように握っていた。
スマホを膝に置いているが、画面は黒いまま。
――麻酔をしても痛みに耐えた、中学の頃の自分がここにいる。
スーツ姿の若い社会人の女性。
仕事帰りなのだろう、目の下には疲れの影があり、バッグを膝に強く抱えている。
ため息をつくたびに腕に力がこもり、書類の端がくしゃりと折れた。
――数年後、逃れられずに通い続ける未来の自分のように見えた。
そのとき、奥から「キュイーン」と鋭い音。
女の子は母の胸に顔をうずめ、肩を震わせる。
高校生は唇を噛み、制服の布が小さく揺れる。
社会人の女性はバッグを抱く腕に力を込め、爪が白く浮き上がった。
三人三様の反応。
けれど、美保の目にはそれが一つに重なって見えた。
過去の自分、思春期の自分、未来の自分。
この待合室そのものが、彼女の人生を映す鏡のように思えた。
番号札を握る指先に汗がにじみ、紙が柔らかく歪んでいく。
秒針の音が「カチ、カチ」と大きく響き、心臓の鼓動と重なった。
外から見れば、静かに座る女子大生。
だが内側では、次に呼ばれるその瞬間を想像するだけで、胸が縮み上がり、全身が細かく震えていた。
# 第四章 待合室
番号札を握る手のひらは、じっとりと濡れていた。
薄い紙は汗を吸って柔らかくなり、折り目が白く浮き出している。
ソファに腰を下ろしたはずなのに、落ち着くどころか背中は冷房の風に晒されながらも汗で張りつき、服が肌に貼りついた。
明るい白壁、観葉植物、整然と並んだ雑誌ラック。
見た目だけは清潔で静かな待合室。
けれどそこに漂うのは、消毒液の匂いと、押し殺された不安の気配だった。
――キュイイイーン。
突如、奥の診療室から鋭い音が走った。
金属が歯を削る甲高い音。
耳ではなく、骨の奥にまで入り込み、頭蓋を震わせる。
続いて、吸引器の「ゴォォォ」という低い唸り。
さらに「チョロチョロ」と水の流れる音が加わる。
音の層が重なり、待合室の壁全体が微かに震えているように思えた。
「……っ」
誰かの息を呑む音。
そして、泣き声が混ざった。
「いやだぁ……! いやぁぁっ!」
小さな女の子の声。掠れて、必死に、割れるように。
その瞬間、待合室全体が凍りついた。
雑誌をめくっていた手が止まり、ページは中途半端に折れ曲がったまま。
新聞を広げていた指は硬直し、紙面がぴんと張り詰めた。
時計の秒針の音さえ一瞬遠のき、全員が同じ方向を見つめた気がした。
小学生の女の子は母の袖をぎゅっと握り、肩を震わせて顔をうずめる。
高校生は制服の袖を握りしめ、唇を噛んでうつむいた。
社会人の女性はバッグを抱く腕に力を込め、留め具がきしむほど握り締めている。
――過去。
――思春期。
――未来。
目の前の三人が、すべて自分の延長に見えた。
小学生の泣き声は、小学校の診療台で泣き叫んだ自分の声。
高校生の沈黙は、中学生のとき痛みに耐えて涙をこらえた自分。
社会人の女性の硬い表情は、数年後の自分の姿に思えた。
「はーい、がんばってね〜……もう少しですよ」
衛生士の優しい声が扉の奥から響く。
けれどその直後、再び「キュイイイーン」と甲高い音。
泣き声はさらに高く割れ、壁を通して突き刺さる。
待合室の空気が一層重くなった。
誰もが呼吸を潜め、ただ音と声に支配されている。
美保の心臓は早鐘を打ち、鼓動が耳の奥で響く。
背中には冷たい汗が流れるのに、こめかみからは熱い汗がにじみ落ちた。
息を吸うたびに薬品の匂いが肺に刺さり、喉がひゅっと細くなる。
番号札を握る指先は震え、紙がぐしゃりと音を立てた。
その小さな音ですら、場の静けさを破った気がして、美保は慌てて指を緩める。
――この沈黙のあとに、私の名前が呼ばれる。
それを思った瞬間、心臓が胸を突き破りそうに跳ねた。
診療室の奥ではまだ「キュイーン」が続いている。
泣き声は時折途切れ、また小さく高く響く。
そのたびに待合室全員の肩が揃ってすくみ上がる。
凍った時間。
重たい空気。
そこに座る人々の呼吸が一斉に浅くなり、空調の風音すらやけに大きく聞こえた。
美保はバッグを膝に抱きしめ、番号札を握ったまま、ただ目を伏せるしかなかった。
胸の奥では、次に呼ばれる恐怖がじわじわと大きく膨らんでいく。
# 第五章 治療台の上
### 1. 名前を呼ばれる瞬間
「美保さーん」
受付の女性の声が、待合室に柔らかく響いた。
だが美保には、それが鋭い鐘の音のように胸を打ち、鼓動を一気に早める。
一瞬、空気が固まった気がした。
周囲の患者たちは視線を落としているのに、なぜか自分だけが注目されたような錯覚。
背筋が強張り、指先の血の気が引く。
番号札を握った手に力が入り、紙がぐしゃりと音を立てた。
立ち上がろうとすると、膝が重く、靴底が床に貼りついたようでうまく動かない。
――けれど逃げ道はない。
美保は意を決して、足を前へ出した。
### 2. 診療室へ歩く
扉を開いた瞬間、空気が一変する。
冷房の風が頬を撫で、消毒液の匂いが肺に落ちる。
そこに混ざる金属の冷たい匂いは、待合室よりも濃く、喉をひりつかせた。
床は白く磨かれ、ワックスの光沢がやけにまぶしい。
一歩ごとに靴底が「きゅっ」と鳴り、静寂に溶け込んで響く。
数メートルの廊下が、永遠に続く道のように長く感じられた。
奥から「キュイーン」と甲高い音が響き、次いで「ゴォォ」という吸引音が続く。
そのたびに足取りは重くなり、心臓の音は一歩進むごとに速さを増していく。
――もうすぐ、自分の番。
胸の中でその言葉が繰り返され、呼吸が浅くなる。
### 3. 診療室の光景
白い壁に囲まれた診療室は明るすぎて、目が眩むほどだった。
壁際のトレーには、銀色の器具が整然と並んでいる。
ピンセット、探針、ミラー、そして細長い麻酔の注射器。
どれも磨かれていて、光を反射して冷たくきらめいた。
ハンドピース――ドリルはホースに吊られて揺れている。
その小さな先端が光を弾くたび、美保の胸がぎゅっと縮み、喉がひゅっと狭まった。
漂うのは消毒液の匂い、金属の匂い。
そこに微かに混じる湿った匂いは、直前まで治療を受けていた誰かが残していったものだろう。
口を開いて呻いた息の余韻が、まだ空気のどこかに残っている気がした。
### 4. 治療台に座る
「どうぞ、こちらへ」
促されるまま、革張りの椅子に腰を下ろす。
背もたれは冷たいはずなのに、触れた瞬間に汗でぬるりと張りついた。
腰を預けた途端、そこにはもう後ろへ退く余地がなかった。
やがて椅子がゆっくりと傾き始める。
頭が後ろに倒れていくと、視界が天井から無影灯へと切り替わる。
大きな円形の光源は、まだ点灯していないのに、すでに眼差しのような威圧を放っていた。
「逃げられない」という言葉が、光の輪から突きつけられているように思えた。
視界の端で、銀色の器具やホースが揺れている。
ドリルの先端がわずかに動くだけで、心臓が勝手に跳ね、耳の奥に鼓動が響いた。
汗がこめかみを伝い、首筋へ落ちていく。
その冷たさすら不快で、体は強張り続けていた。
### 5. 医師の声と「アーン」
「本日どうなさいましたか」
「……奥歯が、虫歯になってしまって……」
「痛みはありますか」
「……冷たいものが少し……」
「そうですか。では少し見せていただきましょう」
先生は無影灯の角度を整え、手袋をはめ直した。
その一連の動作が「これから始まる」という現実を突きつけ、美保の胸を強く締めつけた。
「はい、それではお口の中見ていきますね。アーンしてください」
穏やかな声。
しかし美保には、その言葉が「逃げ場の扉を閉ざす合図」のように聞こえた。
唇が震えた。
喉は乾ききってひゅっと細く、呼吸は乱れ、声にならない息がもれた。
それでも、美保は必死に口を開いた。
「……アーン」
次の瞬間、無影灯がぱっと点る。
白い光が一気に口の奥まで流れ込み、銀歯が反射してきらめいた。
クラウンは鏡のように光を返し、インレーは星屑のようにきらめき、奥の黒い穴までも白く浮かび上がった。
「はい、いいですよ〜」
衛生士の柔らかな声がすぐそばから響く。
その優しさすら、美保には「もう観念してください」という意味にしか聞こえなかった。
冷たいミラーが唇に触れた。
ひやりとした感触が背筋に走り、全身を強張らせる。
――始まってしまった。
胸の奥で小さく響く声。
美保は震えながら、ただ口を開け続けるしかなかった。
# **第六章 削られる瞬間**
ミラーが奥歯に差し込まれ、無影灯の白い光が美保の口腔を鮮やかに照らしていた。
先生が探針の先で右下の奥歯を軽くつつく。
「……大きいですね」
落ち着いた声が、美保の胸に重く沈んだ。
「神経までは届いていないと思います。ただ、実際に削ってみないと分からないですね」
――削ってみないと分からない。
その言葉が頭の奥で反響し、胸をきつく締めつけた。
先生は続けた。
「痛かったら手を挙げてください。その時点で麻酔をしますから」
呼吸が止まった。
最初からではない――?
痛みを感じてから……?
喉が細くなり、声はかすれた。
「……そ、それって……」
「大丈夫。無理に我慢させることはありません。合図をすれば止めますから」
先生の声は穏やかだが、美保の心臓は落ち着くどころかさらに速さを増していた。
衛生士が横からやさしく添える。
「美保さん、もし痛かったらすぐ手を挙げてくださいね。先生、ちゃんと見ていますから」
ほんの少し救われるようでいて、震えは止まらない。
膝の上で握った両手は白くなり、汗でじっとりと濡れていた。
先生が無影灯を整えた。
光の輪が口の奥を射抜き、銀色の器具が一斉に輝く。
ホースに吊られたドリルの先端が小さく揺れ、光を弾いた。
「はい、それでは始めます。アーンしてください」
唇が震え、喉は渇ききっていた。
それでも美保は大きく口を開ける。
「……アーン」
無影灯がぱっと明るさを増し、銀歯が白く反射した。
クラウンは鏡のように光を返し、インレーは小さな星座のようにきらめいた。
虫歯の黒い影までも、光にさらされるように浮かび上がる。
先生の手が器具のトレーに伸びる。
銀色がカチャリと触れ合い、乾いた音が診療室に響いた。
背筋が強張り、呼吸が浅くなる。
ホースの先に吊られたドリルが持ち上げられる。
揺れるたびに細い管が軋み、先端は鋭く光を放つ。
美保は視界の端でそれを見ないようにしても、光は嫌でも目に入った。
先生はハンドピースを指で確かめ、カチ、と小さな音を立てる。
そして――ペダルに軽く足をかけた。
――ウィィィィン……
まだ弱い回転。
試運転のような低い唸りが空気に広がった。
それだけで胸が縮み、指先が震えた。
「はい、行きますよ」
再びペダルが踏み込まれる。
――キュイイイイーン!
甲高い音が一気に跳ね上がり、鼓膜を震わせた。
待合室で聞いていたあの音が、今は自分の口の中に向かっている。
――痛いのか、痛くないのか。
――その答えは次の瞬間にやって来る。
美保は冷たい汗を頬に伝わせながら、顎を震わせ、必死に口を開け続けた。
# 第七章 痛みの奔流(最終仕上げ版)
「それでは削っていきますね」
先生の落ち着いた声が降りた瞬間、美保の胸の奥は冷たく締めつけられた。
――キュイイイイーン。
甲高い音が空気を裂き、耳の奥に突き刺さる。
ドリルの先端が光を弾きながらゆっくりと近づいてくる。
歯に触れた。
「ガリッ」という感触が骨を通して頭の奥にまで響いた。
まだ痛みはなかった。
だが振動のひとつひとつが脳髄に直接伝わるようで、全身が凍りついた。
――まだ大丈夫。
そう自分に言い聞かせる。
けれど、「次の瞬間に来る」という予感が、胸を圧迫し続けた。
数十秒。
「キュイーン」「ガリリッ」という音が繰り返され、冷たい水が流れ込む。
バキュームの「ゴォォ」という低音が重なり、舌の奥に金属と水の味が広がった。
呼吸が乱れ、胸が浅く上下する。
一分。
奥歯の根元がじんわりと熱を帯びるように痛み始めた。
眉間に皺が寄り、目尻に涙がにじむ。
「大丈夫ですか〜? 痛かったら左手を挙げてくださいね」
衛生士の優しい声が響く。
美保の左手は膝の上で小さく震えていた。
さらに削りが深くなる。
ズキンッ!
「ひっ……!」
鋭い痛みが神経を突き抜け、頭の奥に閃光が走った。
全身が跳ね、革張りの椅子がぎゅっと軋む。
美保は反射的に左手を高く挙げた。
指先まで震え、汗で濡れた掌が光を受けて光った。
――止まって!
必死に願った。
だがドリルは止まらない。
「もう少しですからね〜」
先生の落ち着いた声。
「はーい、大丈夫、大丈夫〜、痛くない、痛くない〜」
衛生士の囁き。
――違う、痛い。
頬が紅潮し、涙が頬を伝って落ちる。
こめかみからは冷たい汗が首筋へと流れ、顎は痙攣し、小刻みに震えた。
「っ……あ……っ……」
喉から声にならない呻きが漏れる。
痛みは波のように押し寄せた。
一瞬弱まったかと思えば、また鋭く突き刺さる。
その繰り返しが、時間を歪ませていく。
数秒が数分に引き延ばされ、光・音・匂い・痛みがぐるぐると混じり合った。
焦げた匂いが鼻腔を突き、金属の味が舌に広がる。
「キュイーン」が頭蓋を振動させ、涙が耳元へと流れ落ちた。
「もうちょっとですよ、頑張ってね〜」
先生の声がまた降りる。
それは優しさではなく、終わりの見えない宣告のようだった。
左手は空中で震え続けている。
だが誰も止めてはくれない。
美保の視界は涙で霞み、白い無影灯の光がにじんで揺れた。
冷や汗と涙に濡れながら、顎を大きく「アーン」と開けたまま、
ただ耐えることしかできなかった。
# 第八章 削り終わった後
――キュイイイーン。
甲高い音が一瞬高まり、ふっと途切れた。
診療室の空気が静まり返る。
だが、美保の鼓動は乱れたまま、胸の奥で早鐘を打っていた。
口の中にはまだ振動の余韻が残り、歯根の奥がじんじんと熱を帯びている。
顎は力が抜けきらず、小さく痙攣していた。
「……はい、よく頑張りましたね」
先生の声は穏やかだった。
だが、美保の目尻には涙が溜まり、頬を伝って流れ落ちていた。
冷たい汗は首筋を濡らし、背中のシャツが革張りの椅子にじっとり貼りついている。
「虫歯は取り切れました。神経のすぐ近くまで行っていましたね。しばらく染みるかもしれません」
冷静な説明。
――やっぱり、そんなに深かったんだ。
胸の奥に重く不安が落ちる。
「お口の中、吸いますね」
衛生士がチューブを差し込み、「ゴォォ」と低い音で水と血を吸い上げる。
先端が歯肉に軽く当たり、くすぐったいような圧力を感じる。
冷たい水が流されると、焦げた匂いと薬品の味が溶け合って舌に残った。
「はい、一度うがいしてください」
紙コップに注がれた水を受け取り、口に含む。
冷たい水が熱を持った奥歯に触れた瞬間、「ズキッ」と鈍い痛みが走った。
「っ……」
思わず肩がすくみ、小さな吐息がもれた。
口をすすぐと、水はすぐ赤みを帯び、金属の味が混じる。
吐き出すと、血の混じった水が白い陶器のボウルに広がり、泡立って流れていった。
美保はその色を見て、胸の奥がまた冷たくなる。
鏡の中に一瞬だけ自分の顔が映った。
目尻は赤く腫れ、頬は涙と汗で濡れている。
額から流れ落ちた汗が顎先に溜まり、ぽとりと落ちた。
「大丈夫ですか? 苦しくなかったですか」
衛生士がタオルで口元をそっと拭う。
その柔らかさにまた涙がにじみ、頬が熱くなる。
美保は小さくうなずいた。
けれど胸の奥はまだ波打ち、両足は無意識に突っ張ったまま。
膝の上で握りしめていた左手は、力が抜けきらず小刻みに震えていた。
治療は一段落した。
だが、美保の中には「やっと解放された安堵」と「これで本当に終わりなのか」という不安がまだ渦巻いていた。
# 第九章 帰り道と友人たち
診療台から降りたとき、足は自分のものではないように重かった。
会計の窓口に立つだけで息が乱れ、渡された領収書に記された「後日・充填処置」の文字が胸を突いた。
――今日は削っただけ。まだ終わっていない。
ガラス扉を押し開けると、夕暮れの風が顔を撫でた。
外の空気は確かに自由のはずなのに、喉の奥にはまだ消毒液と血の匂いがこびりつき、舌先には金属の苦みが広がっていた。
耳の奥には「キュイイイーン」という残響がこびりつき、右下の奥歯は今もじんじんと脈打っていた。
街のざわめきも、夕焼けの赤も、どこか遠い。
ただ「痛かった」という記憶が現実として体にまとわりつき、肩を重く沈めていた。
---
数日後。
大学のカフェテラス。
木陰を渡る春の風が氷を揺らし、グラスの澄んだ音を立てていた。
周囲の学生たちの笑い声や談笑が響くが、美保には遠い世界のように聞こえた。
「ねえ美保、この前歯医者行ったんでしょ?」
彩香がストローを指でくるくる回しながら、さりげなく切り出した。
「……うん」
美保はグラスを持ち上げ、氷を揺らす音で間を稼ぐ。
「で? どうだった? やっぱ痛かった?」
美咲が身を乗り出し、目を丸くした。
「んー……まあ、普通かな」
美保は肩をすくめ、軽く笑った。
「うそだー!」
奈緒がすかさず声を上げる。
「顔に出てるって。絶対痛かったでしょ」
「そうそう。さっき水飲んだとき、肩ビクッてしてたよね?」
彩香が冷静に突っ込む。
「……っ」
図星を突かれ、美保は言葉を失い、氷を揺らす音だけが手元に響いた。
「いや……そんな大げさじゃ……」
ごまかそうとするが、三人の視線が容赦なく注がれる。
「ほら! やっぱ痛かったんでしょ?」
美咲が笑いながらテーブルを叩く。
「私のときもそうだったもん。麻酔したのに涙止まんなかったし!」
「……」
美保は目を伏せ、喉が渇いた。
心臓の鼓動が早まり、背中にあのときの冷や汗がよみがえる。
沈黙は、何よりも雄弁だった。
観念するように、美保は小さく息を吐いた。
「……めっちゃ痛かった。ほんとに」
言葉にした瞬間、胸の奥に鋭い痛みが再び走る。
左手を必死に挙げたのに止まらなかったこと。
「もう少しですからね〜」という先生の声。
涙で滲んだ視界。
――全部がよみがえった。
「ほらね!」
三人が同時に声を上げ、テーブルの上に笑い声が弾けた。
「どんな感じだった?」
美咲がさらに追い打ちをかけるように尋ねる。
「……最初は響くだけだった。でも、だんだんズキンって神経に刺さってきて……」
声はかすかに震えていた。
「左手、思いっきり挙げたのに止まってくれなくて……涙止まらなくなって……」
「うわ、それは地獄」
奈緒が大げさに両手で頬を押さえる。
「わかるよ! 私も“もう少し”って言われて全然終わらなかった」
「私なんかさ、隣の子供が“いやだー!”って泣いてて、それとキュイーンが重なって……ほんと心折れた」
美咲が苦笑まじりに言う。
「私もうがいのとき血混じってさ、うわぁってなった」
彩香が静かに付け加える。
三人が口々に体験を重ね、笑い合った。
そのとき奈緒が大げさに口を開け、「アーン」と言った。
奥歯のクラウンが春の光を受けて鋭く光る。
「ここ、ほんっと痛かったの!」
「わ、でかっ!」
美咲が覗き込み、自分も負けじと下のインレーを見せる。
「私も、アーン」
下の奥歯に銀が光る。
「これ大学入ってから。冷たい水飲むたびズキッてして、“あ、終わった”って悟ったの」
彩香も控えめに口を開け、奥の銀を見せる。
「私なんか小学生の頃からあるよ。手挙げても止めてくれなかったの、今でも忘れられない」
銀歯が三人分、日差しを受けて一斉に光った。
テラスは明るく、笑い声は軽やかだった。
美保も笑顔を作った。
「……みんなも大変だったんだね」
だがその笑みの裏で、心臓はまだ診療室に置き去りにされていた。
耳には「キュイーン」、頬には涙の跡、背中には冷たい革張りの感触――。
領収書に記された「後日・充填処置」という文字が胸の奥で光り続けていた。
氷の入った水を一口含む。
右下の奥歯に刺激が走り、肩が小さく震えた。
奈緒がすぐ気づいて口を尖らせる。
「やっぱまだ痛むんじゃん!」
「……うん」
小さく認める声は、春のざわめきにかき消された。
---
笑い声と光の中で、ただ美保だけが、あの日の診療台に縛り付けられたままだった。
この記事の目次

昭和生まれ