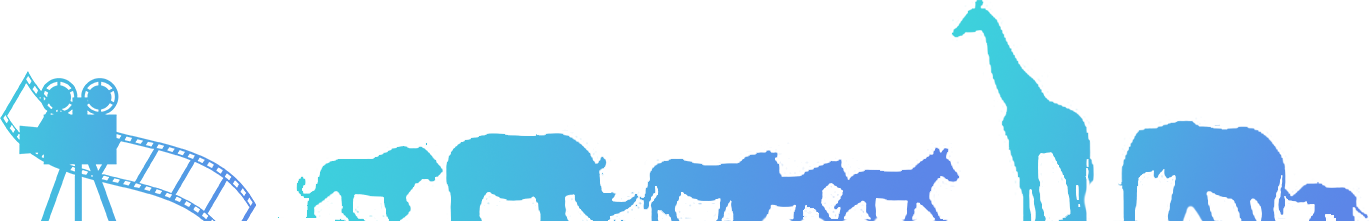藤沢 真央 20歳大学生

第一章 学食でのざわめき
藤沢真央は、大学の友人たちの間で「清楚な美人」とよく言われる存在だった。
派手さはない。だが、肩にかかる艶のある黒髪と、すっと通った鼻筋、切れ長の瞳には凛とした雰囲気がある。
整った白い歯並びは、笑うたびに清潔感を際立たせた。普段から虫歯は少なく、歯磨きも几帳面にしてきたからこそ、今日胸に渦巻く不安は自分でも意外だった。
昼休みの学食は、ざわめきに包まれていた。
トレーを運ぶ学生たちの列、食器が触れ合う金属音、椅子の脚が床を擦る「きゅっ」という音。
窓際のテーブルに差し込む春の光が、真央の白い横顔を淡く照らしていた。
「ねぇ、聞いてよ」
向かいに座る美咲が、フォークでサラダのトマトを突きながら声を落とす。わざと秘密めかす調子だった。
「先週、歯医者に行ったんだけどさ……奥歯、けっこう深くなっててね、削られたんだよ」
奈緒が大げさに眉をひそめる。
「え、また虫歯? やだなぁ……。あたし去年やったけど、口をずっと“アーン”でしょ? あれ、もう拷問」
そう言いながら肩を抱えて身を縮める。
「麻酔はしてもらったの」美咲は続ける。
でもね、と前置きして、耳に手を当てた。
「キュイーンって音がね……頭の奥まで突き抜けるの。骨に響いて、涙腺が勝手に開くのよ」
「ひぃっ!」奈緒は大げさに耳をふさぎ、「やめてよ、今お昼だよ」と笑う。
彩香がストローを回しながら頷いた。
「私も去年やったよ。先生に“ここはよく噛む場所だから丈夫に”って言われて、銀詰めになった」
それから、いたずらっぽく口を大きく開く。
「アーン」
蛍光灯の光を受け、奥の銀が一瞬、星のようにきらりと光った。
「うわ、本当に見える!」奈緒が顔を寄せる。「思ったよりピカピカじゃん」
「でしょ。でも仕方ないよね。長持ちするなら」彩香は肩をすくめる。
真央も笑顔を作って頷いた。
「うん……ほんとだね」
整った白い歯並びが覗く。その歯を友人に褒められたこともある。けれど今日は、心の奥で血の気が引いていくのを止められなかった。
——これ、私も入れられるのかな。
——あの音を聞きながら、ずっと“アーン”で耐えるのかな。
「それでね」美咲はスプーンを握り直しながら言う。
「先生、『痛かったら手を挙げてね〜』って言うんだけど……挙げても止まらないことあるのよ」
「あるある!」奈緒が強くうなずく。「“もう少しだからね〜”って、永遠に言うんだよ」
三人の笑い声が弾け、テーブルの氷がカランと揺れる。
真央も笑った。唇は笑っているのに、心の奥では汗が滲んでいた。
「待合室でね、小さい子が泣いてたの。“いやだぁ!”って叫んだ瞬間に、奥からキュイーン。返事みたいだった」
美咲の身振りに、奈緒が「怖すぎ!」と大声を出す。
真央は黙って水を口に含んだ。
氷の冷たさが舌に触れた瞬間、右下の奥歯に幻の痛みが走る。
歯並びはよく、虫歯はほとんどなかったはずなのに——そこにだけ黒い影が潜んでいる。
「でも終わったらスッキリするよ」美咲が言う。「冷たい水もしみないし、噛める。世界が変わるの」
「……それはいいなぁ」
真央の声は小さく震えていた。
胸の奥で“終わった”という言葉が、遠い灯のように点っていた。
チャイムが鳴り、三人は立ち上がる。
「真央、早めに行きなよ。浅いうちなら痛みも少ないって」
「夜LINEするね!」彩香が手を振る。
席が空き、ざわめきが遠のく。
真央はコップの氷を転がし、左の奥でそっと噛んだ。
窓の外の若葉が光を弾く。
椅子を引いたときの「きゅっ」という音が、今日は不思議とキュイーンには聞こえなかった。
第二章 夜の不安
その夜。
講義の復習をしようと机に向かっていたはずの真央は、ページをめくる手を止めていた。
黒々とした文字は意味を結ばず、ただ線の模様にしか見えない。
部屋は静かで、窓の外からかすかに原付のエンジン音が流れてくる。
それすら耳の奥で歪み、キュイーンの音に似て聞こえた。
真央は両手を胸の前で組み、深呼吸を一度。けれど呼吸は浅く途切れ、胸の鼓動ばかりが速まっていく。
——見ておこう。今のうちに。
意を決して、洗面所へ立った。
蛍光灯をつけると、冷たい白が一気に広がった。
鏡に映る自分は、昼間の学食で友人たちと笑っていた顔とは違い、どこか青白く硬い。
肩に落ちる黒髪の隙間から、切れ長の瞳が強張ってこちらを見返してくる。
「……アーン」
口を大きく開け、指で右の口角を押さえて覗き込む。
手鏡を動かし、ライトの光を当てる角度を探る。
そこにあった。
右下の一番奥。白い歯並びの中に、不自然に暗い穴。
小さな影は、思っていたより深く、広がっていた。
舌で触れる。ざらっ。
表面の凹みは、他の歯の滑らかさとあまりに違いすぎる。
爪の先でなぞろうとして、すぐに指を引っ込めた。
——これ以上触れたら、奥に響いてしまいそうで。
コップに水を汲み、口に含む。
ビリッ。
冷たさが染みて、神経に針を突き立てられたみたいな痛みが走った。
「っ……!」
肩をすくめ、思わず鏡から目を逸らす。涙が頬に滲み、顎を伝って落ちていく。
「やばい……」
声に出した瞬間、現実が重くのしかかった。
——行かなきゃ。
——でも、怖い。
真央の頭の奥で、幼い日の記憶が勝手に開いた。
眩しい無影灯。押さえつけられた両腕。
口角に触れる冷たいミラー。
そして、耳を裂くようなキュイーン。
泣き叫ぶ声。それは他人ではなく、自分の声。
「いやだ……」
唇から小さな声が漏れた。
頬を伝う涙は冷たかったが、その冷たささえ恐怖を深めた。
鏡に映る歯並びは整っている。白く清潔で、自分の誇りのひとつだった。
それなのに、右下の奥だけが黒い影に侵されている。
その一点が、全体の調和を乱し、胸を不安で満たしていた。
「浅いうちに行けば痛みは少ない」
学食で美咲が言った言葉が頭をよぎる。
でも——“浅い”ってどこまで?
——手を挙げても止まらなかったら?
洗面台に手をつき、蛇口の銀色を見つめる。
そこに映る光が、未来の銀の詰め物と重なって見えてしまい、胸がぎゅっと締め付けられた。
もう一度口を開く。
「……アーン」
顎が震える。喉の奥がつまる。
目尻に涙をにじませながら、それでも鏡の中を覗き込む。
——今日、見てしまった。
見なければよかった。けれど、見たからこそ、逃げられない。
電気を消す。部屋は暗くなり、静けさが増す。
ベッドに横になり、天井を見つめる。
まぶたを閉じると、光の輪が浮かび、耳の奥でまたキュイーンが伸びる。
「……行こう」
小さな声で呟いた。
胸に手を当て、深く息を吸う。
——終わりのある呼吸。吸って、吐いて。
それを繰り返しながら、真央は目を閉じた。
第三章 歯科医院の入口
午後の講義を終え、商店街を抜けた真央は、ゆっくりと歩を進めていた。
八百屋の呼び込みの声、焼き鳥屋から漂う煙、豆腐屋のラジオの演歌。
いつもなら心地よい生活のざわめきが、今日は遠い世界のものに感じられる。
胸の奥で心臓が早鐘を打ち、歩く速度に追いつかない。
角を曲がった瞬間、白いタイル張りの建物が視界に入った。
「○○歯科クリニック」。
磨かれたガラスの自動ドア、その奥に並ぶ観葉植物と受付の机。
青い文字の看板が、春の陽射しを反射して硬く輝いている。
その瞬間——
——キュイーン。
扉越しに漏れる甲高い音。
胸の奥を針で突かれたように真央は立ち止まった。
鼓膜が熱を帯び、耳鳴りと混ざって世界が一瞬揺れる。
右下の奥歯が、まだ治療されてもいないのに「ビリ」と疼いた気がした。
「……っ」
喉が詰まり、息を飲む。
全身の血が足先に落ちていくような感覚。
視界の端が白く霞む。
——あの音。
幼い日の断片が、勝手に蘇る。
白い無影灯。押さえつけられた腕。
口角に触れた冷たいミラー。
泣き叫ぶ声——あれは、紛れもなく自分だった。
取っ手に手を伸ばす。
指先は汗で濡れ、ガラスに触れた瞬間つるりと滑る。
慌ててスカートで手のひらを拭き、もう一度握る。
小さなガラス片のように震える自分の指先が、目の前の透明な扉に映っていた。
——行かなきゃ。
——でも、行きたくない。
胸の奥で二つの声が綱引きをする。
外の風が背中を押す。だが足は床に縫い付けられたみたいに動かない。
「……大丈夫」
自分に言い聞かせるように小さく声を出す。
その声は掠れ、かえって不安を際立たせた。
美咲の言葉が頭に浮かぶ。
——終わったあとは世界が変わるよ。冷たい水もしみないし、ちゃんと噛めるんだよ。
その言葉にすがるように、真央は肺いっぱいに空気を吸い込んだ。
震える肩を押し下げ、ゆっくりと吐き出す。
一度。二度。三度。
そして、意を決して自動ドアを押した。
静かにガラスが開き、内部の冷気が顔を撫でた。
薬品の匂いが喉を刺し、世界の空気が一変する。
日常から切り離された、歯科医院という異質な空間が、真央を飲み込んでいった。
第四章 待合室
一歩足を踏み入れると、冷房の風が頬にまとわりついた。
背中を伝っていた汗が一気に冷え、鳥肌が広がる。
磨かれた床は蛍光灯を映し、靴底が「きゅっ」と小さな音を立てた。
「診察券をお願いします」
受付の女性の笑顔は柔らかい。けれどキーボードを叩く音が、なぜか乾いた金属音に聞こえる。
手渡された番号札を受け取るとき、真央の指は濡れて紙をふやけさせそうだった。
——ただの紙切れ。なのに、鉄塊のように重い。
待合室には三人の患者がいた。
入口近くでは、小さな女の子が母親にしがみついて泣いている。
「いやだ……いやだぁ!」
甲高い声が壁に反響し、真央の胸に突き刺さる。
母親は必死に「大丈夫だからね」と背を撫でているが、その声も震えていた。
すぐに——奥の診療室から「キュイーン」。
泣き声に応えるようなタイミング。
女の子はさらに顔を母の胸に埋め、体を震わせた。
ソファの一角には、スーツ姿のOLが座っている。
バッグを膝に抱え、片手で頬を押さえたまま。
広げた雑誌はページを行き来するばかりで、視線は宙をさまよっていた。
指先はわずかに震え、真央にはその姿が未来の自分に重なって見えた。
一番奥には、老人が新聞を広げている。
だが目は紙面を追わず、遠くを見ている。
新聞紙をめくる「かさり」という音だけが、やけに鮮明に耳に届いた。
白い壁。薬品と消毒液の匂い。
観葉植物の緑も、花の写真のポスターも、この場所の緊張を和らげてはくれなかった。
時計に目をやる。
秒針の「カチ、カチ」という音が、胸の鼓動と重なって頭蓋に響く。
時間は進んでいるのに、真央の中では止まっているように長い。
膝の上で番号札を握りしめる。
爪が食い込み、紙が折れ曲がる。
喉はからからに渇き、唾を飲み込むこともできない。
——“アーン”と口を開けさせられる未来が、すでに迫っている。
「いやだ! いたいのいやぁ!」
女の子の泣き声。
すぐに奥から「キュイイーン」。
待合室全体が震えた気がして、真央は思わず肩をすくめた。
膝の上の指が震え、番号札がカサカサと音を立てる。
——私も、すぐあの中へ。
胸の奥に冷たい刃が突き刺さるような感覚。
そして——
「藤沢真央さーん」
名前を呼ばれた瞬間、世界が凍りついた。
周囲の音が消え、空気が張り詰める。
他の患者たちの視線が一斉に突き刺さり、喉が固まる。
心臓が痛いほど跳ねる。
脚を動かそうとしたが、鉛のように重く、立ち上がった瞬間、椅子の革が汗で貼りつき「ぺり」と小さな音を立てた。
呼吸は細く途切れ、声は出ない。
それでも足は、重さを引きずりながら診療室の奥へと進んでいった。
第五章 治療台の上
名前を呼ばれ、扉をくぐった瞬間、世界の密度が変わった。
廊下は想像以上に静かで、天井のダクトから一定の風が流れ、冷気が腕の産毛を逆立てる。床のワックスが無影灯の白を反射し、通路は光の帯になって先へ伸びていた。右手の小窓からは、うっすら夕方の気配。日常の光は遠のき、ここには“治療の時間”だけが支配している。
「こちらへどうぞ」
丸い名札に〈森山〉とある歯科衛生士が、柔らかい笑顔で手を添えた。
案内されたユニットはパステルブルーで、背凭れの革はひんやりと張りがある。隣のユニットからは低い話し声と、時おり短くキュイーンが震え、壁越しに空気の薄膜だけがかすかに揺れて返ってくる。
「お荷物はここに置いてくださいね。眼鏡、そのままで大丈夫です」
森山はテキパキと動き、紙のエプロンを真央の首に当て、小さな金属クリップで留めた。鎖の先端が鎖骨に触れてひやり。その温度だけで心臓が一段高鳴る。
ユニット脇のトレーには、ステンレスの器具が整列している。ピンセット、探針、デンタルミラー、コットンロール、青と赤の細い紙(咬合紙)、スリーウェイシリンジ。ホースの先には角度のついたハンドピース。銀色の細い首が光を跳ね返し、先端には米粒ほどのバーがついている。——最も嫌いな相手。
腰を下ろすと、背中に冷たい革が吸い付く。浅く呼吸をすれば、紙エプロンが胸にふわりと貼りつく。
「椅子、倒していきますね」
背もたれが電動で静かに沈み、視界は天井の白い穴(丸い無影灯)のみになる。ライトの輪郭が徐々に近づき、まぶたの薄皮を通しても明るさが刺さる。
——逃げ道が、なくなる。
そんな言葉が胸の底でごく小さく鳴った。
「担当の石川です。よろしくお願いします」
椅子の左側から現れた白衣の医師は、名札に〈石川〉。低めでよく通る声だった。
マスクの上の目元は穏やかで、視線はぶれない。器具のトレイに一瞬だけ目を落とし、すぐに真央に戻ってくる。
「はい、それではお口の中見ていきますね、アーンしてください」
その一言が、逃げ場のない合図に思える。真央は顎の震えを飲み込むように、そっと唇を開いた。
「……アーン」
上から光が降り、口腔の陰が一気に剥がれる。
デンタルミラーが唇の端に触れる。冷たい。頬の内側が薄く引き伸ばされ、鏡の円が奥まで光を運ぶ。探針の先が噛む面の溝をチッ、チッと軽くなぞるたび、歯の芯にごく小さな電気が灯るような違和感が走る。
「右下の一番奥、噛む面ですね……縁が崩れて、軟らかくなっている所があります」
石川は短くメモをとり、角度を変えてもう一度、軽く探針を当てる。
(当たっているのは表面のはずなのに、脳が“奥”を想像してしまう)
——そこ、そこは、だめ。
心の中で言葉にならない声が浮かんでは消える。
「乾燥させます」
森山がスリーウェイシリンジの先を少し傾け、シューと細い乾いた風を歯の上に吹きかけた。
瞬間、むき出しの冷気が象牙質へ触れ、ビリと細いハープの弦がはじけるような感覚が走る。肩が、わずかに跳ねた。
「大丈夫ですよ。呼吸、ここに合わせましょう。吸って……吐いて……」
森山は真央の鎖骨あたりに手をかざし、胸の上下に合わせて自分の呼吸をゆっくり示す。
真央は視線を天井の白い輪に固定し、意識的に息を送り込む。吸って、吐く。
紙エプロンが胸の上でわずかに上下する。汗がこめかみをつたって、耳の裏に集まる。
「水、いきます」
バキュームの先端がそっと口角に当たり、ゴォォと低い音で唾液と水を吸い上げる。舌の縁をかすめる冷たさと、微かな金属の味。
——“アーン”のまま、声が奪われていく。
吐きだしたい言葉は喉の奥に留まり、音ではなく空気だけになる。
石川の指が軽く顎に触れ、視線がわずかに右下へ誘導される。
「照明、もう少し落とします」
ライトの角度が変わり、狙い澄ました白が一点を刺す。
その鋭さに呼吸が再び浅くなり、真央は肘掛けを握る手に力を込めた。掌はすでに湿っている。
——視線を天井に。数を数える。
一、二、三……四、五。天井クロスの細い継ぎ目、微妙な陰影。
数えながらも、探針のコツ、コツという骨伝導のような響きは逃さない。
「はい、確認できました」
石川が椅子をほんの少し上げ、トレーに探針を置く金属音がカチと響く。
「右下の奥歯、噛む面の虫歯がやや大きめです。縁も脆くなっているところがあるので、形を整える必要があります」
言葉は静かで、余計な飾りはない。ただ、内容が胸に沈む重さを持つ。
(やっぱり、“やや大きめ”なんだ)
真央は喉の奥で小さく息を呑んだ。
白い歯並びの列で、そこだけが黒い影を持つ。
整っているはずの“わたし”の一部に、ぽっかりと空いた異物。
その違和感は、そのまま不安の形をとる。
「痛みが出たときの合図は、左手を挙げるでお願いします。僕と森山が見える位置で。呼吸はゆっくり。視線は天井に置いたままで大丈夫」
石川は、目線を落とさないよう真央の正面から短くリズムを刻むように言う。
森山が「はい、合図はすぐ見えますからね」と優しく重ね、吸引管の位置を微調整する。
ユニット横のホースが微かに揺れ、ハンドピースが持ち上げられる。
石川が指で先端のバーを確かめ、水平をとる。
足元でペダルがコツと小さく鳴った。
——キュ……
空回しの試運転。ほんの一瞬、回転が立ち上がりかけて止む。
刃はまだ触れていないのに、背中の筋肉が反射的に縮む。
肘掛けの縁で親指の爪が白くなるほど力が入っているのを、真央は遅れて知る。
(逃げたい)
(でも、終わらせたい)
二つの声がふたたび胸の奥で綱引きを始める。
呼吸のリズムが乱れかける。森山がすぐに気づき、ささやく。
「吸って……吐いて……そう、ゆっくりで大丈夫ですよ。もう少しですからね〜」
その言葉は、儀式の開始を告げる合図にも聞こえた。
「乾燥、もう一度。……はい」
シュー。
さっきよりも冷たさに身構えていたせいか、今度は肩が跳ねない。
(大丈夫、大丈夫)
天井の白を見据え、真央は“終わりのある呼吸”を反復する。
石川が視野を確かめ、ライトの影をわずかに動かす。
「では……」
短い間。
ハンドピースが静かに真央の視界から消え、右下の奥、見えないところへ位置を取る。
耳の奥で、遠い部屋のキュイーンが一つ、細く伸びて消える。
——次は、自分の番。
紙エプロンの上で、胸がわずかに上下する。
舌は、無意識に退避する場所を探している。
頬の内側は吸引管でやさしく牽かれ、口角はミラーでそっと広げられている。
“アーン”はもう形を選べず、ただ精いっぱいの開きに固定された。
石川の声が、白い光の向こうから届く。
「では、始めます。呼吸はそのまま。痛かったら左手を挙げて教えてください」
返事をしようとするが、声は与えられていない。
代わりに、真央は左手の指を少し持ち上げ、合図の準備だけを示した。
森山が小さく頷く気配がする。
足元のペダルが、もう一度踏み込まれる。
回転音が、さっきよりも確かな立ち上がりを見せる。
——キュイーン。
甲高い音が細い刃を震わせ、空気と歯のあいだに薄い膜を張る。
それが、いま、自分の口の中へ入ってくる。
真央は、まぶたをぎゅっと閉じた。
視線は天井に——意識は呼吸に。
吸って、吐いて。
胸の奥で、見えない小さな決意がかたちを取る。
第六章 麻酔なしの宣告
「では……今日は麻酔を使わずに治療していきますね」
石川先生の声は、落ち着いていて柔らかかった。
けれどその一言は、真央の心臓を一気に締め付けた。
「……麻酔、しないんですか?」
自分でも驚くほど小さな声が喉から漏れた。
先生は目を細め、ゆっくり頷いた。
「はい。今回は、削るのは浅いところです。麻酔をかけるほどではありませんよ。麻酔をすると治療のあとにしびれが長く残ってしまうんです。食事やお話も違和感が出ますからね」
少し間を置いて、さらに言葉を重ねる。
「もちろん、削るときに“響く”ような感覚が出るかもしれません。でも、それはほんの短い時間ですし、すぐに終わります。痛みを我慢するためじゃなくて、“必要なところだけ”を削るためなんです」
森山衛生士がそっと真央の肩に手を置き、にこりと微笑んだ。
「大丈夫ですよ。つらかったら左手を挙げてくださいね。合図を見たらすぐに止めますから。……安心してください。もう少しですからね〜」
——ほんとうに大丈夫?
胸の奥で不安が膨らむ。理屈では理解できても、心は震えていた。
「それでは……お口を大きく開けてください」
石川先生の声は、日常会話の延長のように穏やかだった。
「……アーン」
真央は顎の震えを抑えながら、大きく口を開ける。
無影灯の白が一段と強まり、口の奥がさらけ出される。
冷たいミラーが唇を押し広げ、吸引管の先端が舌に触れた。
逃げ道のない体勢。
先生がフットペダルに足を乗せる。
――キュイーン。
甲高い回転音が空気を切り裂き、骨に響く。
真央の全身が硬直し、指先が小刻みに震えた。
第七章 痛みの襲来
――キュイーン。
甲高い回転音が無影灯の光と重なり、真央の全身を覆った。
刃先が歯に触れる。
ジジジ……。
細かな振動が奥歯から顎の骨へ、耳の奥へと伝わる。
最初は“響き”。まだ耐えられる。
だが次の瞬間——
ズキンッ!
「ひっ……!」
針で神経を突き抜かれたような痛みが走り、背中が大きく跳ねた。革張りの椅子が軋む。
指が肘掛けに食い込み、爪が白く変色する。
涙が瞬時ににじみ、視界がぐにゃりと歪む。
唇の端から唾液が糸を引き、紙エプロンに滴り落ちた。
「左手を挙げてくださいね」
——挙げる。必死に。
森山衛生士がすぐに「はい、ありがとうございます」と応じる。
だが、キュイイインと音は止まらない。
「もう少しですからね〜。大丈夫ですよ」
石川先生の穏やかな声が頭上から降る。
だがその言葉と同時に刃はさらに深く入り、
ズギャッ!
「っああぁぁ!」
鋭い痛みが神経束を貫き、こめかみまで突き抜ける。
胸が勝手に大きく上下し、冷や汗が耳の裏をつたって首筋へ落ちていく。
バキュームが低くゴォォと唸り、唾液と削りかすを吸い上げる。
そこに混じる金属の味、焦げたような匂いが鼻を突く。
「呼吸、ゆっくりでいいですよ。吸って、吐いて……」
森山の優しい声が波のように寄せてくる。
だが真央の身体は制御を失い、顎は震え、舌は逃げ場を探して彷徨っていた。
左手をもう一度高く挙げる。
視界の端で森山の顔が見えた——でも、ドリルは止まらない。
「もう少しですからね〜」
石川の声。
その「もう少し」が、果てしなく長く伸びる。
痛みは点ではなく、塊になって奥歯の中心で脈打つ。
ズキンズキン。
涙が頬を伝い、顎に溜まってぽたりと落ちる。
「いたくない〜、いたくないですよ〜」
衛生士の子守歌のような声が響く。
けれど真央の胸は乱れ、肺は浅く、呼吸は小刻みに切れていた。
——止まらない。
——逃げられない。
真央は、瞼をぎゅっと閉じ、大きく口を開け続けるしかなかった。
第八章 時間の地獄
――キュイーン。
音が、骨を通じて頭蓋の奥まで染み渡る。
回転する刃が歯を抉るたび、世界が裂ける。
一分。
まだ始まったばかり——のはずだった。
だが真央には、一秒が針で心臓を刺されるように長い。
時計の秒針は「カチ」と音を立てるたび、耳の奥で増幅し、鼓膜を揺らした。
——永遠。
「呼吸して、大丈夫。吸って……吐いて……」
森山の声。だが肺は空気を拒み、胸が浅く上下するだけ。
三分。
ズギンッ!
刃がわずかに深く入る。神経に直撃したのだろう。
こめかみに雷が落ち、目の奥に白い閃光が弾けた。
「っあぁぁ!」嗚咽が口の奥に渦巻くが、アーンと開いた口は閉じられない。
唾液と涙が混じり合い、頬を濡らし、顎を伝って紙エプロンに黒い染みを作る。
「もう少しですからね〜」
石川の穏やかな声が落ちてくる。
——“もう少し”。
それは約束ではなく、呪いに聞こえた。
五分。
痛みは点から塊へ変わり、奥歯の中心で脈を打つ。
ズキンズキン。
それは心臓の鼓動と重なり、血管全体が痛みに支配される。
鼻に薬品の匂い、焦げた象牙質の匂いが混じり、舌に金属の味が広がる。
——自分の口が、自分ではない異物になっていく。
「いたくない〜、いたくないですよ〜」
森山の声が子守歌のように重なる。
だが痛みは子守られるどころか、さらに強く育っていく。
七分。
冷や汗が額を滴り、耳の裏を伝って首筋に流れる。
背中は汗で椅子に貼りつき、動くたび「ぺたり」と音を立てる。
脚は硬直し、つま先まで痺れて感覚がない。
目尻からは涙が途切れなく落ち、視界は滲んで白い光の洪水になる。
「もう少しですからね〜」
またその言葉。
耳に焼きつき、頭蓋の内側を回り続ける。
——どれだけ待っても、終わりは来ない。
“もう少し”が、永遠の合図に変わっていく。
十分。
時間の感覚が崩れる。
五秒が五分に、十秒が十分に。
痛みだけが唯一の時計。
キュイイイン。
刃が奥へ進むたび、神経に雷が落ちる。視界に火花が散り、喉から押し殺した呻きが漏れる。
「っ……んんっ……!」
左手は必死に宙を掴むように上がる。
だが止まらない。
「もう少しですからね〜、大丈夫ですよ」
その声が優しくなるほど、真央の心は絶望に沈む。
唇は乾き、舌は逃げ場を失い、胸は乱れ、呼吸は刻むように浅く途切れる。
涙、唾液、冷や汗が混ざり合い、口の中は金属味で満たされている。
——終わらない。
——ここは地獄。
真央は瞼を固く閉じ、大きく口を開けたまま、ただその拷問の時間に身を晒していた。
第九章 治療直後の放心
――キュイーン。
最後の一音が空気に溶け、ゆっくりと回転が止まっていった。
石川先生がハンドピースを静かにトレーへ置く。カチリという金属音が、やけに鮮明に響いた。
音が消えたはずなのに、真央の耳の奥ではまだ甲高い残響が鳴っていた。
顎はこわばったまま開ききっていて、閉じ方すら忘れてしまったようだ。
全身の力が抜けず、椅子に押しつけられた背中がじっとりと汗で貼りついている。
「はい、うがいしてくださいね」
森山の優しい声が届く。
口角から器具が離れ、バキュームの低い唸りも止む。
真央はぼんやりと、指示に従って口を閉じた。
顎が重く、動かすたびに筋肉がきしむ。
口に水を含むと、わずかに金属の味と血の匂いが混じる。
「……」
うがいをして吐き出す。
流れ落ちた水の中に、削られた粉が白く舞った。
鏡に映る自分の顔を想像して、頬が熱くなる。
涙で濡れたままの目尻。
紅潮した頬。
息苦しさに乱れた唇。
——清楚だと呼ばれる自分の面影は、どこにもなかった。
「よく頑張りましたね」
石川先生が淡々と、しかし少し柔らかく言った。
それが褒め言葉であることは分かる。
だが、真央の心にはただ「やっと終わった」という虚脱だけが残っていた。
紙エプロンを外すと、鎖骨に当たっていた金属クリップの冷たさの跡がまだ残っている。
背中を椅子から起こすと、「ぺたり」とシャツが革張りに張り付いて剥がれる音がした。
その小さな音さえ、羞恥と疲労を混ぜ合わせたように心に響いた。
手鏡が差し出される。
右下の奥に、白ではなく銀が埋め込まれている。
光を反射して、小さな異物がきらりと光った。
真央は視線を逸らし、ただ小さく頷いた。
——痛みは過ぎ去った。
だが心臓の鼓動はまだ速く、身体は小刻みに震えている。
世界は静かなのに、自分の中だけが騒音で満ちていた。
第十一章 帰宅と余韻
玄関の扉を閉めた瞬間、外のざわめきが遠のいた。
自宅の空気は、医院の冷たさとは違い、どこか甘く温かい匂いに満ちていた。
台所から漂うのは味噌汁の香り。出汁と味噌の混じったやわらかな匂いが、鼻腔に広がる。
「おかえり、真央」
母の声。
振り返ると、エプロン姿で鍋をかき混ぜながらこちらを見ていた。
「……ただいま」
言葉に力が入らず、吐息のように出た。
「どうだった? 麻酔したの?」
問いかけに、真央は一瞬だけ視線を伏せた。
「……してない。しないで削られた」
母の手が止まった。驚きが表情ににじむ。
「えっ……それ、痛かったでしょう?」
「……うん」
それ以上、言葉にできない。唇を噛むと、顎がまだ重く震えた。
母は鍋を火から外し、椅子を引いて座るよう促した。
「でも、よく頑張ったわね」
その言葉に、真央の胸の奥がじんわりと緩んだ。
食卓に味噌汁と炊きたてのご飯が並ぶ。
湯気が立ちのぼり、白い煙のように天井へ消えていく。
さっきまでまとわりついていた薬品と金属の匂いが、徐々に家庭の匂いに塗り替えられていく。
箸を取り、味噌汁を口に含む。
舌の上に広がる出汁の旨味。
……しみない。
冷たい水に怯えていた自分を思い出し、ふっと力が抜けた。
「……大丈夫そう?」
母が心配そうに尋ねる。
「うん……大丈夫。なんか……終わったんだって、やっと思えた」
器を置くと、腕の力が抜けて肩がだらりと落ちた。
椅子に凭れ、深く息を吐く。
背中にまだ“あの革張りの椅子”の感触が残っている。
でも、それも徐々に家庭の温かさに薄められていくようだった。
窓の外で、夜の風が木の葉を揺らす。
真央はその音に耳を澄ませながら、心の中で小さく呟いた。
——もう少しですからね。
先生の声がまだ残響のように響く。
けれど今は、味噌汁の温かさがその声を静かに覆い隠していった。
終章 学食のテーブルで
数日後。
昼休みの学食は相変わらずざわめきに満ちていた。
窓際の席に腰を下ろすと、蒸気に包まれた味噌汁の匂いが鼻をくすぐる。
隣に座った美咲が、待ってましたとばかりに声を潜めた。
「ねぇ、真央。行ったんでしょ? 歯医者」
その一言に、奈緒と彩香も同時に顔を寄せる。
「えっ、どうだったの?」「麻酔した?」
真央は一瞬、スプーンを握り直した。
あのキュイーン、涙、汗、そして「もう少しですからね〜」の声が一気に甦る。
だが、それと同時に“終わったんだ”という実感が背中を支えた。
「……麻酔、しなかった」
静かに言うと、三人が一斉に目を見開いた。
「うそ!」「大丈夫だったの?」「めっちゃ痛かったんじゃ……」
矢継ぎ早に飛んでくる声。
真央は少しだけ笑った。
「……うん、痛かった。正直、泣いた」
そう言って頬を指で触ると、あの日の涙の熱さがまだ微かに残っている気がした。
美咲が息を呑み、そして苦笑した。
「やっぱり……でも、無事に終わったんだね」
「うん。冷たい水もしみない。ご飯も普通に食べられる」
スプーンですくったカレーを口に運ぶ。
舌の上で広がる味。あの日とは違い、ちゃんと味わえる。
「それだけで、すごく幸せ」
真央の言葉に、奈緒が「分かる〜」と笑い、彩香が「銀は入っちゃったの?」と口を開く。
「……うん。右下の奥に、きらっと」
そう言って、ほんの少しだけ口を開けてみせる。
光を受けた銀が、小さく反射した。
奈緒が驚いた顔をし、すぐに冗談めかして言った。
「でも似合ってるかも。ほら、勲章みたいな?」
「なにそれ」
三人の笑い声が弾けた。
真央も一緒に笑った。
笑うと、整った歯並びの奥で光る小さな銀が、自分の新しい一部になったように感じられた。
怖かった時間も、泣いたことも、終わった今では思い出に変わっていく。
——もう少しですからね。
あの日何度も聞いた言葉が、心の中でやわらかく響いた。
それは今、恐怖の呪いではなく、「終わりが来る」という約束の証のように聞こえた。
窓の外で春の風が若葉を揺らしていた。
真央は小さく息を吸い、友人たちとまた笑い合った。
そして、もう一度カレーを口に運んだ。
味は、やっぱり温かくて、確かなものだった。
この記事の目次

昭和生まれ